東北旅行の最後に行きたかった場所の一つとして旧くりはら田園鉄道を訪問しました。
時代の流れで非電化→電化→非電化という運命をたどり、最後は経営改善のため非電化になったのにも関わらず「くりでん」という愛称を残すために「くりはら“田園”鉄道」という社名になりましたが、惜しくも2007年3月31日にラストランを迎えました。

かつてのJRとの接続駅である石越駅前からくりでん代替バスに乗ります。

路線名はそのまま「くりはら田園線」でした。

線路跡は踏切跡などの一部を除き、ほぼ全線に渡って残っていました。

途中、バス停以外でも乗降できるフリー乗降区間があるおかげからかお年寄りの利用者が多かったです。
この利用者の方にとって、この代替バスはなくてはならないものなのでしょうね。

旧栗駒駅にやってきました。

駅舎はなくなり、「駅前」だったと思われる場所だけが開けていました。

かつては駅前だったと思われるお店で栗たい焼を買ってみました。
このように手軽に食べられる物が売っているお店が今もあることは有り難いことですね。

旧栗駒駅近くにあるみちのく風土館の中にあるくりでんの展示を見てから、再びバスに乗り込みました。

鉄道公園になっている若柳駅にやってきました。

隣は農産物直売所になっています。

駅舎は閉まっていて、乗車会のある時にしか入れないようでした。

レールバイクもあるんですね。
旧三木鉄道にもサイクルトロッコがありますけど。

せっかくここまで来たのに、ホームに入れなかったのは残念だったなぁ。

ただ、新たな公園施設を作っているようだったので、今後は三木鉄道記念公園のように開館している日が増えることを期待しましょう。

くりでん代替バスとは違う市民バスで新幹線の駅へ。
新幹線の駅を経由するとは思えないほど小さなバスでした。
おかげで荷物が座席に引っかかって乗り降りするのも大変でした。

くりこま高原駅から新幹線に乗車することに。
在来線や鉄道とは接続していない、残念な駅です。
例えるなら、市営地下鉄や北神急行のない場合の新神戸駅と言えば分かっていただけるのではないでしょうか。
当初の計画通り、もしこの駅がくりでんと交わる場所に作られていたら、くりでんも今頃観光鉄道になって存続していたんじゃないかと少しやるせない気持ちになりました。

驚いたのは駐車場の広さです。
この規模の駐車場が線路の両サイドに広がっていました。
地方から来た人がこれを見たら「この地域は公共交通をないがしろにしているのか」と思われても不思議ではありません。
藻谷浩介さんが粟生線シンポジウムで言っていた「車でも行ける、電車でも行ける」を実現させて欲しかったと心の底から思わせる駅でした。
これでは「くりでんはお荷物だけど、新幹線の駅はお飾り道具として欲しかった」と言っているも同然ですよ。

E5系やまびこで東京へと向かいます。

奮発してグランクラスに乗車しました。

グランクラス和軽食もとても美味しかったです。

お酒も飲みました。
自分で運転しなくて良いので、アルコールを気にせず飲めるのが鉄道の醍醐味ですよね。

鉄道の旅をするのに地元ではない大きな駅や現地までは車で行くという方も中にはいらっしゃいますが、車の運転が出来ない私は毎回公共交通機関のみを使っての移動となります。
そのため、毎回公共交通機関の有り難さを実感することになりますが、今回もそれを実感することの出来る充実した旅行となりました。
旧くりはら田園鉄道を訪ねて。
テーマ:鉄道の事例
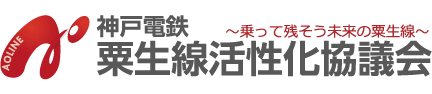


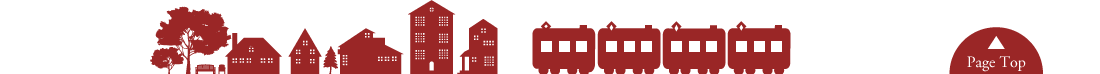
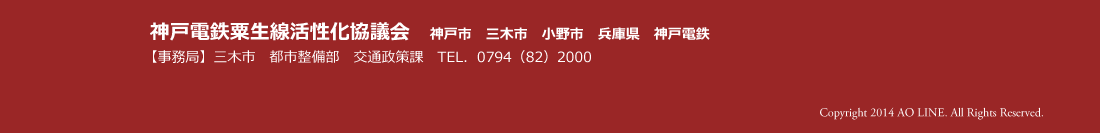
この記事へのコメント